事業譲渡は、中小企業のM&Aにおいても頻繁に利用されるスキームですが、最もトラブルが発生しやすいのが「従業員の扱い」です。
- 「事業譲渡の際、従業員も自動的に譲渡されるのか?」
- 「譲渡を拒否することはできるのか?」
- 「退職した場合、会社都合扱いになるのか?」
- 「従業員が同意しない場合、企業はどう対応すべきか?」
買い手企業としては、事業に関わる人材も含めてスムーズに引き継ぎたいと考える一方、売り手企業の従業員にとっては、突然の「会社変更」という重大な問題になります。
こうした背景から、事業譲渡時における従業員の取り扱いについては、法的・実務的な観点から一度しっかり整理しておく必要があります。
ぜひ最後まで読み進めて、実務で役立つ知識を身につけてください。
「退職したいけど、その後の生活が心配…」という方には、無料で相談できるスグペイの活用もおすすめです。
スグペイでは、給付金の申請サポートをはじめ、退職後の生活設計までトータルでサポートしてもらえます。
条件を満たせば、最大310万円の失業保険を受け取れる可能性もあります。
合わせて読みたい
-

-
【最大310万円】失業保険の増額サポート「スグペイ」の実際の評判・口コミを徹底調査
続きを見る
事業譲渡による退職は、原則として「自己都合退職」扱い
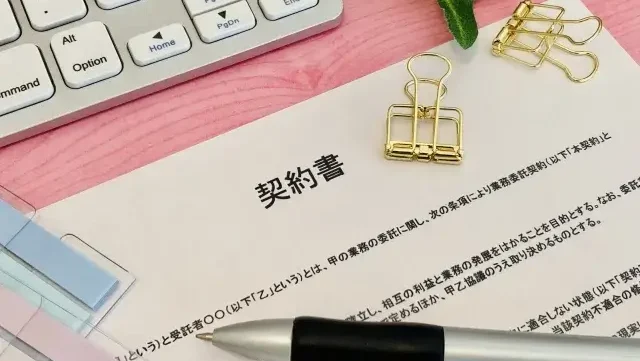
事業譲渡(企業の合併・買収)が行われる場合、従業員の雇用は通常、買収先の企業へそのまま引き継がれます。したがって、事業譲渡に反対して自ら退職を選んだ場合は、基本的に「自己都合退職」とみなされます。
労働契約の継続が提示されているにもかかわらず、それを本人の意思で拒否する形になるため、会社側から見れば「引き続き雇用する用意があったのに退職した」という扱いになるからです。
ただし「会社都合」または「特定理由離職者」と判断されるケースもあります
以下のような事情がある場合は、自己都合ではなく、実質的に会社都合や特定理由離職者として扱われる可能性があります。
- 譲受会社の勤務地が大きく変わる(通勤困難になる)
- 労働条件(賃金・勤務時間・職種など)が明らかに不利益に変更される
- 雇用契約が事実上リセットされ、勤続年数がリセットされる
- 新会社への転籍が強制に近い形で迫られた
- 会社が「転籍を断るなら退職しかない」と通告している
これらに該当する場合、ハローワークでは「やむを得ない理由による離職(特定理由離職者)」として扱われ、会社都合とほぼ同等の条件で失業給付(待機7日後すぐ受給開始)が可能になります。
参考:厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
最終的にはハローワークが決める
離職票には会社が「自己都合退職」と書くことが多いですが、「会社都合」または「特定理由離職者」になるかどうかはハローワークの聞き取りで決まります。
「譲渡先での労働条件が変わる(または受け入れを拒否した理由)」を具体的に説明すると、再判定してもらえるケースが多いです。
書面(事業譲渡通知、労働条件変更通知など)があると非常に有効です。

譲受先での条件が変わる、勤務地が遠くなる、転籍に不安があるなどの理由があるなら、自己都合とは限らず、会社都合に近い「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
「会社都合退職」「自己都合退職」「特定理由離職者」の違い

失業保険を受け取る際に最も重要なのが「退職理由の区分」です。
同じ“退職”でも、会社都合退職・自己都合退職・特定理由離職者の3つで、受給開始時期や給付内容が大きく異なります。
とくに「特定理由離職者」は誤解されやすい項目で、一見“自己都合”に見えても、やむを得ない事情がある場合には会社都合に近い扱いとなることがあります。
ここでは、厚生労働省の基準をもとに、3つの退職区分の違いと判断基準を解説します。
「会社都合退職」とは、企業側の都合により従業員が退職を余儀なくされること(特定受給資格者)
代表的な例としては、経営悪化によるリストラや倒産などがありますが、それだけではありません。
- 会社の倒産や事業縮小による解雇
- リストラ(整理解雇)
- 契約社員・派遣社員の雇い止め
- 契約期間が満了した(会社が申し出)
- 給与の不払い、または不当な賃金カット
- 希望退職制度による合意退職
- パワハラやいじめなどにより退職を余儀なくされた
- 転勤や配置転換により通勤が困難になった(往復通勤時間が4時間以上)
- 長時間労働が常態化し、改善されなかった
参考:厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
雇用契約と実際の労働条件に大きな食い違いがある場合や、パワハラ・いじめなど職場環境が原因でやむを得ず退職する場合も、「会社都合退職」として扱われることがあります。
うつ病などの病気で退職する場合でも「会社都合退職」になる場合があります。詳しくはこちらの記事で解説しました。
合わせて読みたい
-

-
【最大310万円】うつ病など病気での退職でも失業保険を最短7日で受け取る方法
続きを見る
「自己都合退職」とは、従業員が自らの意思で会社を辞めること
たとえば、結婚や出産、育児、転居といったライフイベントのほか、親の介護や自身の健康上の理由など、家庭や個人の事情による退職が該当します。
- 職場環境や人間関係への不満
- キャリアアップや転職、起業を目的とした退職
- 契約期間が満了した(本人が申し出)
- 本人の病気やケガ、または家族の介護が必要になった
- 結婚・出産・育児など私的な事情による退職
- 懲戒処分により退職を命じられた
- 事業譲渡(企業の合併・買収)が行われる場合
キャリアアップを目指した転職や、職場環境への不満から退職を選ぶ場合も、自己都合退職として扱われます。
参考:厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
「特定理由離職者」とは一見すると自己都合退職に見えるが、実際にはやむを得ない事情によって離職した人
「特定理由離職者」とは、つまり、「会社都合退職」と「自己都合退職」の中間に位置する扱いです。
やむを得ない正当な事情により自己の意思で退職した人を指します。該当すると、自己都合退職と異なり給付制限なし(待機7日後)で失業給付の受給が可能です。
たとえば契約期間の満了により雇用が継続されなかった場合や妊娠・出産・病気・家族の介護など、本人の努力では回避できない理由で退職せざるを得なかったケースが該当します。
また、通勤困難や転居、配偶者の転勤などによる離職もこのカテゴリーに含まれます。
特定理由離職者に該当する主なケース
- 健康上の理由による離職
体力の低下、疾病・負傷、障害、視力・聴力・触覚など感覚機能の低下により就労継続が困難になった場合。 - 妊娠・出産・育児に伴う離職
妊娠・出産・育児を理由に退職し、雇用保険法第20条第1項の「受給期間延長措置」を受けた場合。 - 家庭の事情の急変による離職
父母の死亡・疾病・負傷等による扶養や、親族の常時看護が必要となった等の事情で離職を余儀なくされた場合。 - 別居の継続が困難になった場合
配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となり離職した場合。 - 通勤が不可能・困難になった場合
・結婚に伴う住所変更
・育児に伴い保育施設の利用・親族への保育依頼が困難
・事業所の通勤困難地への移転
・自己の意思に反する転居・移転の強制
・鉄道・軌道・バス等の廃止や運行時間変更等で通勤不可
・事業主命令の転勤・出向に伴う別居を回避するための離職
・配偶者の転勤・出向・再就職に伴う別居回避のための離職 - 契約期間の満了により雇用が継続されなかった場合
契約社員・アルバイト・パートなどの有期雇用契約において、定められた雇用期間が終了したにもかかわらず、会社と労働者の間で「次の契約更新が行われなかった」場合。
本人に責任はないが、契約があらかじめ決められた期間で自然に終了した場合。つまり、更新の見込みがなかったケース。
例:「今回の契約は6か月で終了します」と最初から明示されていた。
- 希望退職の募集に応じた離職
企業整備等による人員整理での希望退職募集に応じて離職した場合
(ただし「特定受給資格者(会社都合)」に該当しないケース)。
参考:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
特定理由離職者に認定されると、自己都合退職者とは異なり、
待機期間7日後からすぐに失業給付を受け取れる(給付制限なし)というメリットがあります。
これは「本人に責任のない退職」と判断されるため、会社都合退職に近い優遇措置が取られているためです。
ただし、認定にはハローワークでの聞き取りや証明資料(診断書・転居証明書など)が必要になる場合があります。
そのため、退職理由に「やむを得ない事情」がある場合は、離職票の記載内容を確認し、必要に応じて修正を申請することが重要です。
「会社都合退職」「特定理由離職者」の方が失業保険が早く給付される
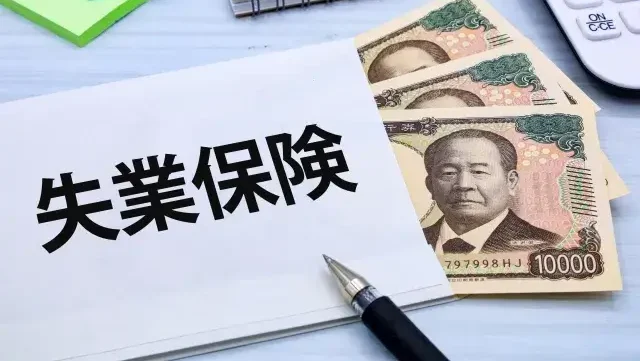
失業保険の支給時期は、退職理由によって大きく変わります。
会社都合で退職した場合は、自己都合退職よりも早く基本手当の支給が始まります。この違いを正しく理解しておくことで、経済的な不安を最小限に抑えることができます。
会社都合退職では、ハローワークで求職申込みを行った後、7日間の「待期期間」を経てすぐに失業保険の受給が始まります。一方、自己都合退職では、待期期間に加えて「給付制限」として原則1〜3か月の期間が設けられます。

| 退職理由 | 支給の開始時期 | 受給期間 |
|---|---|---|
| 会社都合退職 (解雇・倒産・契約満了など) |
離職票を提出し、求職申込後 7日間の待機期間経過後すぐ |
離職日の翌日から1年間 (その間に所定給付日数分を支給) |
| 自己都合退職 (転職、家庭の都合など) |
離職票を提出し、求職申込後 7日間の待機+1〜3か月の給付制限の後 |
離職日の翌日から1年間 (その間に所定給付日数分を支給) |
| 特定理由離職者 (やむを得ない自己都合退職) |
離職票を提出し、求職申込後 7日間の待機期間経過後すぐ |
離職日の翌日から1年間 (その間に所定給付日数分を支給) |
これだけ覚えておけばOK!
「会社都合退職」「一部の特定理由離職者※1」の方が失業保険が長く給付される

会社都合で退職した場合の、失業保険の給付金額、受給開始時期、受給期間について解説します。
これらの条件は年齢や勤続年数、退職時の状況によって異なるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
失業保険の給付日数は、退職理由(会社都合・自己都合)や年齢、雇用保険の加入期間によって異なります。
「会社都合退職」「一部の特定理由離職者※1」の給付日数(90〜330日)
※スマホ・タブレットの場合は左右にスクロールできます。
| 年齢区分 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | - | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上~35歳未満 | - | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上~45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上~60歳未満 | - | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上~65歳未満 | - | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※1一部の特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
「自己都合退職」「特定理由離職者」の給付日数(90〜150日)
※スマホ・タブレットの場合は左右にスクロールできます。
| 年齢区分 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日(※) | 90日 | 120日 | 150日 | 150日 |
※特定理由離職者は、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得られます。
この表からわかるように、会社都合退職は、自己都合退職に比べて給付日数が大きく優遇されています。特に年齢が高く、かつ勤務年数が長い人ほど、受給日数が長くなる傾向があります。
たとえば、45歳以上60歳未満で20年以上勤めた場合、会社都合であれば最大330日間の給付が受けられます。一方、同じ条件でも自己都合退職だと150日までしかもらえません。

なお、1年未満の勤務であっても、自己都合退職なら原則90日しかもらえません。一方、会社都合退職なら年齢によっては同じく90日受給できることもありますが、それ以外のケースでは対象外となる場合もあるため、注意が必要です。
これだけ覚えておけばOK!
「会社都合退職」でも「自己都合退職」でも「特定理由離職者」でも1日あたりの給付金額は同じ
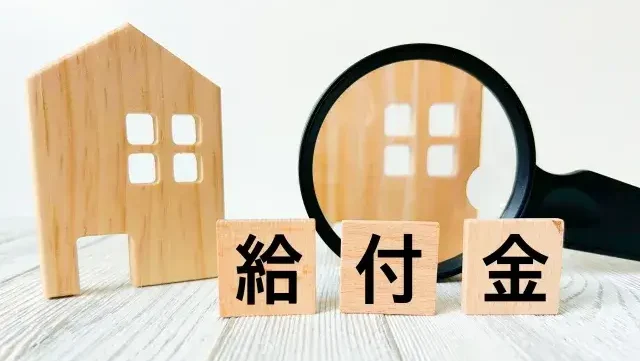
失業保険やその他の公的給付は、「会社都合退職か」「自己都合退職か」「特定理由離職者か」で受給の開始時期や期間に違いはありますが、1日あたりにもらえる金額(基本手当日額)には差がありません。

つまり、条件さえ満たしていれば、自己都合でも会社都合でも特定理由離職者でも、過去の収入に応じて同じ水準の給付が受けられます。退職後の生活が不安という方も、制度の内容を知ることで安心できるでしょう。
平均月収別の支給見込み金額
実際にどれくらいの金額がもらえるのかは、離職前6か月間の平均賃金に基づいて計算されます。以下の表は、おおよその目安です。
| 平均月収 | 毎月の支給見込み額 |
|---|---|
| 20万円 | 10〜16万円 |
| 30万円 | 15〜24万円 |
| 40万円 | 20〜32万円 |
| 50万円 | 25〜40万円 |
| 100万円 | 50〜80万円 |

これらはすべて法律に基づいた正当な給付です。退職後に不安を感じている方は、まずは制度の仕組みを正しく理解し、自分が利用できるかどうかを確認してみるとよいでしょう。
「仕事を辞めたいけど、お金のことが心配…」という方は、無料相談などを活用しながら、事前に情報収集をしておくのがおすすめです。
これだけ覚えておけばOK!
失業給付金が最大310万円受給できる
「スグペイ」を活用するのもあり

退職を決断したとき、頭をよぎるのは「この先の生活、どうしよう」という不安ではないでしょうか。実際、失業保険は働けなくなった人の生活を支える大切な制度ですが、申請方法や書類の準備が複雑で「自分ではよくわからない」「損してしまいそう」と感じる方も多いのが現実です。
とくに、うつ病などの精神的な事情で退職する場合、制度を正しく使えば最短7日で受給が始まり、最大310万円以上を受け取れるケースもあります。しかし、それを実現するには“正確な知識と準備”が不可欠です。
国家資格を持つ社労士などの専門スタッフがあなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請方法や必要書類の整え方をアドバイスしてくれます。
公式サイトでスグペイの詳細を確認する
| 基本情報 | 詳細 |
| 会社名 | 株式会社Amaneku |
| 代表取締役 | 鹿熊 亮甫 |
| 住所 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町4−14 Vort渋谷桜丘ビル 5F |
| 資本金 | 1000万円 |
| 提携社労士事務所 | 小武方社会保険労務士事務所 |
| 提携弁護士法人 | 弁護士法人プロテクトスタンス |
もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事へどうぞ
合わせて読みたい
-

-
【最大310万円】失業保険の増額サポート「スグペイ」の実際の評判・口コミを徹底調査
続きを見る
失業保険を受給するまでの5つの手続き
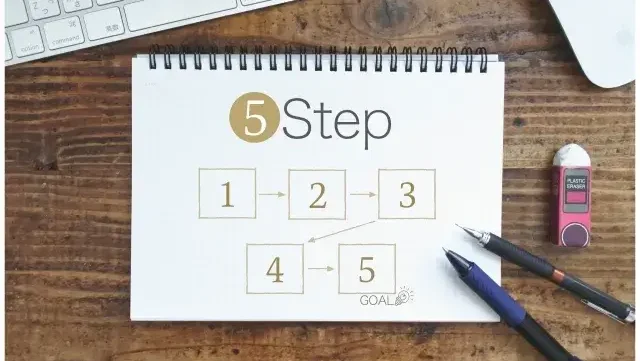
失業保険を受け取るには以下の5つの手順を踏む必要があります。
スムーズに申請を進めるためにも、それぞれのステップで何をすべきかをあらかじめ理解しておきましょう。
step
1必要書類の準備(6種類)
失業保険を申請するには、以下の書類や持ち物を準備しておく必要があります。
- 雇用保険被保険者離職票(会社から受け取る書類)
- マイナンバーカード、または個人番号が記載された書類(通知カード・住民票など)
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)
- 印鑑(認印でOK、シャチハタは不可)
- 証明写真(縦3.0cm × 横2.4cm)を2枚
- 預貯金通帳かキャッシュカード(振込先口座を確認できるもの)
これらを事前に用意しておけば、ハローワークでの手続きもスムーズに進みます。
なお、離職票は会社が作成・交付する書類なので、退職後に忘れずに受け取るようにしましょう。
step
2ハローワークでの求職申込み
準備した書類を持って、最寄りのハローワークに出向き、「求職の申し込み」を行います。
この申し込みが、失業保険を受け取るための最初のステップになります。
なお、ハローワークは居住地によって管轄が異なるため、事前に自分の住所に対応したハローワークを調べておくと安心です。
申し込み時には、離職理由や雇用保険の加入状況などの確認が行われ、受給資格を満たしていれば、後日行われる「雇用保険説明会」の日時が案内されます。
また、ハローワークでは失業保険の手続きだけでなく、履歴書の添削や求人紹介など、再就職に向けた支援も受けられます。わからないことがあれば、遠慮なく相談してみましょう。
step
3雇用保険説明会への参加
失業保険を受け取るには、ハローワークが実施する「雇用保険受給者初回説明会」への参加が必須となります。
この説明会では、以下のような内容が案内されます。
- 受給資格者証の交付
- 失業認定申告書の配布
- 手続きの流れや今後の認定日の説明
制度について不明な点があれば、その場で質問することも可能です。
失業保険を正しく受給するには、制度の内容やルールをしっかりと理解しておくことが大切です。説明会では重要な情報が伝えられるため、集中して聞くようにしましょう。
step
4待機期間の経過と失業認定
失業保険の申請後、まず「待機期間」として7日間が設けられます。この期間中は、どのような理由であっても失業保険は支給されません。
また、受給資格が決定した後は、4週間に1度、ハローワークで失業認定の手続きを行う必要があります。この手続きの際には、認定期間中に2回以上の求職活動実績が求められます。
認定日や活動の記録は、必ずメモしておきましょう。
ハローワークでの手続きや求職活動を忘れてしまうと、失業保険の支給が停止されたり、受給資格を失う可能性があるため、注意が必要です。
step
5失業手当の受給開始
失業認定を受けた後、通常は5営業日以内に、あらかじめハローワークに登録した口座へ失業手当が振り込まれます。
支給される金額は、基本手当日額 × 認定された失業日数で計算されます。
ただし、就職活動の実績が認められなかった場合は、その分の認定が取り消され、支給額が減額されたり、支給されない可能性もあります。
確実に受給するためには、失業手当を受け取りながらも、計画的かつ積極的に求職活動を続けることが大切です。
まとめ|事業譲渡による退職は「自己都合」とは限らない。退職理由の確認が最重要

事業譲渡やM&Aに伴う退職は、原則として「自己都合退職」扱いになります。
これは、譲受会社が「雇用を継続します」と提示しているにもかかわらず、従業員が自ら転籍を拒否して退職する形になるためです。
しかし実際には、以下のようなケースでは「特定理由離職者」や「会社都合退職」として認定される可能性もあります。
- 譲受会社の勤務地が遠くなり、通勤が困難になる
- 賃金・勤務時間・職種などの労働条件が悪化する
- 勤続年数がリセットされるなど不利益な変更がある
- 転籍を強制的に迫られた、または拒否したら退職扱いになった
このような場合、ハローワークの判断次第で会社都合扱いになることも多く、離職票に「自己都合」と書かれていても、再審査で変更される可能性があります。
特に生活の安定を重視する場合は、自分の退職理由がどの区分に当たるのかを確認することが非常に重要です。
退職時には必ず離職票の記載内容をチェックし、実態と異なる場合はハローワークで修正申請を行いましょう。
これだけ覚えておけばOK!
「退職したいけど、その後の生活が心配…」という方には、無料で相談できるスグペイの活用もおすすめです。
スグペイでは、給付金の申請サポートをはじめ、退職後の生活設計までトータルでサポートしてもらえます。
条件を満たせば、最大310万円の失業保険を受け取れる可能性もあります。
合わせて読みたい
-

-
【最大310万円】失業保険の増額サポート「スグペイ」の実際の評判・口コミを徹底調査
続きを見る
